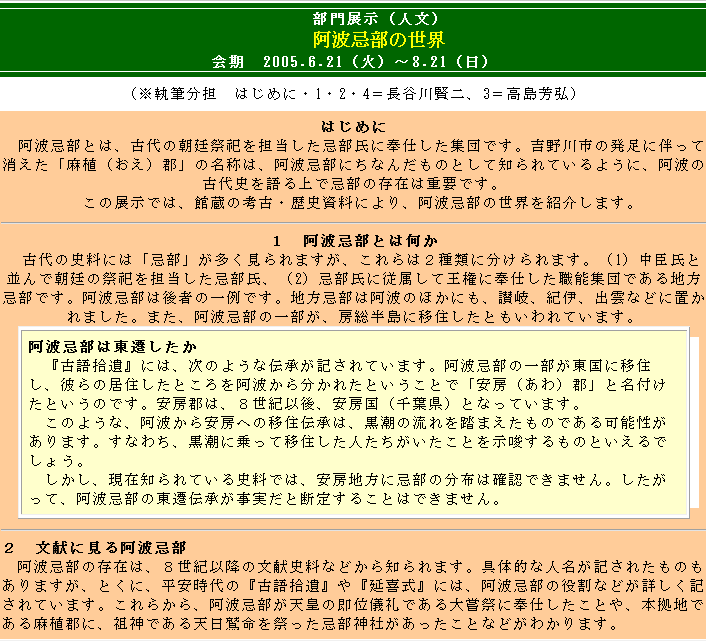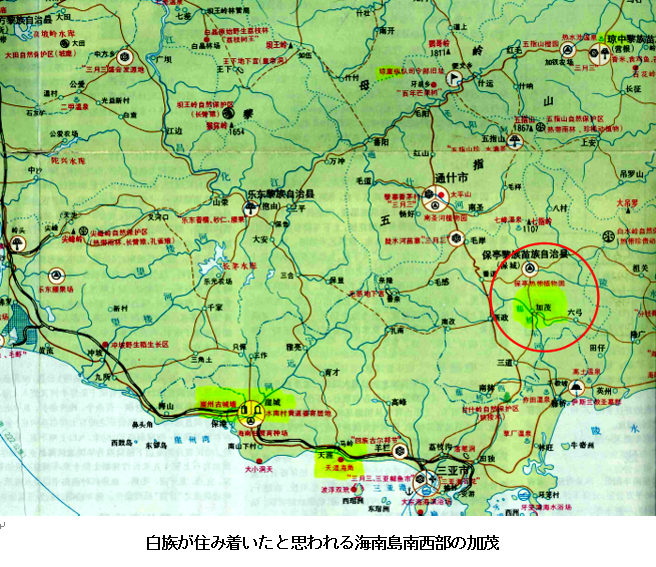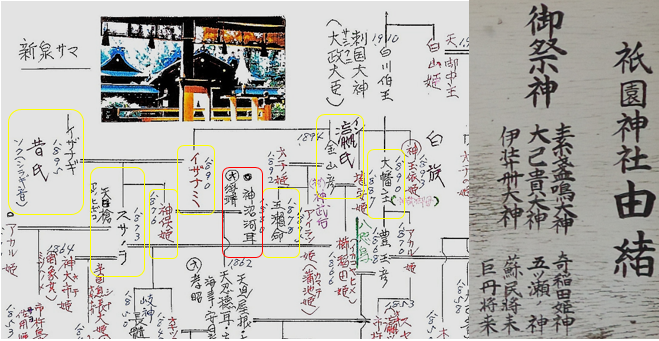394 阿 漕(アコギ) ①
20160904
太宰府地名研究会(神社考古学研究班) 古川 清久
本稿は通説派に堕した久留米地名研究会のHPからバック・アップ(避退)掲載したものです。
本稿は2008年12月1日付で久留米地名研究会のHPに公開した「阿 漕(アコギ)」を再掲載するものですが、今の認識で多少のアレンジを加えています。
なお、初稿は引き続き久留米地名研究会のHPにそのまま掲載されています。
はじめに
伊勢神宮と大和朝廷との間には今なお多くの謎があると言われますが、三重県の津市には“阿漕の浦”(阿漕ケ浦)と呼ばれる浜があります。
本稿はこの「あこぎ」という一つの地名にスポットを当てた民俗学的な小論です。
しかし、これが伊勢神宮の前史を探る一つのきっかけになるのではないか考えており、古代史に想いを巡らせる方にも読んで頂ければと思うものです。
さて、伊勢神宮が現在の地に落ち着くまでには、元伊勢をはじめとしてかなりの前史があることが知られていますが、もしかしたら、この神社も九州から持ち出されたのではないかという疑問が付きまといます。
そういうわけで、本稿は九州の南半分に分布するアコウという印象的な海岸性樹木、阿漕、赤尾、赤木・・・といった地名に関係があり、伊勢の阿漕ケ浦もその一部ではないかという問題に答えようとするものです。
そこで「あこぎ゙」という言葉があります。普通には「あこぎなまね」「あこぎなやつ」などといった使い方がされています。とりあえず『広辞苑』を見てみましょう。
「【阿漕あこぎ】(地名『阿漕ヶ浦』の略。古今六帖3『逢ふことを阿漕の島に引く網のたびかさならば人も知りなむ』の歌による①たびかさなること。源平盛衰記(8)『重ねて聞し召す事の有りければこそ阿漕と仰せけめ』②転じて、際限なくむさぼること。また、あつかましいさま。ひどく扱うさま。狂、比丘貞『阿漕やの阿漕やの今のさへ漸と舞うた、もう許してくれさしめ』。)。『阿漕な仕打ち』③能の阿漕。伊勢国阿漕ヶ浦の漁夫が密漁して海に沈められ、地獄で苦しむさまを描く。」
まずは、この“阿漕”というテーマを取り上げた理由を説明しておこうと思います。
a)釣りとアコウ地名の分布
沖縄から北岸を除く九州の海岸部、島嶼部には赤崎(アコザキ)、赤尾木、赤生木(アコオギ)、阿漕(アコギ)、赤尾(アコオ)、赤木(アコギ)、赤木屋(アコギヤ)、赤木名(アコギメ)といった地名が散見されます。私が始めてこの奇妙な海岸地名に遭遇したのは、二〇年以上も前のことでした。
佐賀県の東松浦半島(東松浦郡肥前町)に魚釣りに行き、大した釣果もないことから、新しい釣場を探して“阿漕”地区に踏み込んだ時でした。
その後も魚釣り(具体的にはサーフのキス釣りや波止からのメジナ=グレ=クロ釣りですが)のために多くの土地を訪ねるようになると、非常に印象的な常緑樹(実際には暴風雨などにより潮水を被った時や年に二度ほど定期的に葉を落としますので半常緑高木とされていますが)をたびたび見かけるようになりました。
具体的には、釣人の多い北部九州を避けて魚釣りと旅とを半々に、佐賀からのんびりと長崎、熊本、鹿児島に南行しているのですが、あまり知られていない漁港の片隅などにアコウ(*)がさりげなく息づいていたのでした。
長崎では五島を中心に長崎式見、大村湾、壱岐、島原半島などに、熊本では八代、葦北郡内(田ノ浦町の波多島地区ほか)から天草諸島周辺に、鹿児島では本土の阿久根、いちき串木野を中心に薩摩、大隈の両半島に、そのほか大分、宮崎にも目立たない入江などに、それなりの数のアコウが分布していたのです。
このアコウという木の生育領域は、ほぼ、和歌山から九州、四国以南に限定されているために全国にはあまり知られていないかもしれません。
![]()
佐賀県唐津市(旧肥前町高串の阿漕地区)
しかし、魚釣りや南の海になじみのない向きにも、鹿児島県の桜島にある古里温泉のアコウは知られています。
林芙美子ゆかりの某観光ホテルには錦江湾に面した崖下に大きな混浴露天風呂がありますが、その傍らに樹齢数百年とも思えるアコウが息ずいているのです。
ここでは、実にアコウの根(気根)の中に体を埋め込みながら温泉に入ることができるのです。
話をさらに拡げますが、一〇年前、私はサーフのキス釣に夢中になっていました。
30㎝超級のキスを求めて鹿児島県の内之浦から、天草下島の南に位置する長島、その天草下島(熊本県牛深市鬼貫崎池田)、さらに五島列島などへと大遠征の釣行を重ねていました。
そしてこの大ギスが釣れる静かな入江やその付近の集落には不思議とアコウがあったのです。
今年(二〇〇四年)の三月にも、強風の中、長崎県のウエスト・コースト西彼杵半島の沖に浮かぶニ島、崎戸島-大島に短時間ながら釣行しましたが、2本のアコウの木が生える静かな漁港で久々に尺超級の越冬ギスを手にしました。
![]()
宮崎県日南海岸の野島神社のアコウ(左)もちろん尺ギスです(右)
このようにアコウに興味を持ちアコウを強く意識しはじめると、九州にはかなりの数のアコウがあることに気付いてきますが、この木の一般的な分布域は沖縄が中心とされています。
四国の足摺岬のアコウも観光地のためか比較的知られていますが、本州におけるアコウの分布は和歌山県だけとされているようです。
しかし、昔は(非常に大雑把な表現ですが)もっと広い範囲に分布していたのではないかとも想像しています。その理由は極めて単純ですが、アコウに関係があると思える地名がその外側(周辺部)にも分布しているからです。もちろん、背景調査を行うことなく地名だけを根拠にアコウの分布域を想像することは根拠に乏しく違法ですらありますが、兵庫県の“赤穂”や三重県津市の“阿漕”さらに多少内陸部とはいえ仙台市の“赤生木”(鹿児島県の笠沙町=薩摩半島先端の町にもこの赤生木という地名があります)などの地名は、やはりアコウ樹の存在と関係があるのではないかと思うものです。
ただし、このような海岸部の地名を考えるときに注意しなければならないことは、海洋民(漁撈民)は非常に移動性が大きく、魚を捕り尽くすとすぐに新たな漁場を求めて移住していく傾向があることです。
そうして、前に住んでいた地名を新たな土地に付けることがかなりあったようなのです。
このため、単純にアコウが生えているということと、地名とが直接的には結びつかないということもあるのです。
しかし、思考の冒険はさらに広がります。この木の名称はほとんど地方名(呼称)のバリエーションを伴っていません。そしてこの地名の分布が、ほぼ、海岸部に限定されていることから見ると、南方起源の海洋民(漁撈集団)が住みついた地域と考えることも可能であり、これらの集団によって既に確立し普遍性を帯びていたアコウという樹名がそのまま地名にまで高まったのではと考えてしまうのです。
b)有明海内部にはなぜアコウがないのか
有明海・不知火海フォーラムの中枢メンバー(当時)である私の立場からしても、多少は有明海との関係を展開すべきでしょう。狭義の有明海(宇土半島三角付近から島原半島布津町付近を結ぶ線の内側)の内部にはアコウの木はないようです。しかし広義の有明海(湯島ラインのさらに外側、天草下島五和町鬼池港から島原半島の口之津町早崎付近を結ぶ線の内側)の外側、口之津町早崎半島先端部にはアコウの群落があります。
また、その線の内側に浮かぶ湯島(熊本県天草郡大矢野町湯島-1637年の島原の乱では農民一揆〔キリシタン?〕側が談合を行ったことから“談合島”の別名があります)にも、やはりアコウの群落があります(湯島小中学校付近)。湯島ラインの内側を有明海と考える向きもありますので、この意味でも文字通り有明海の外側にアコウが存在していることになるのです。
さらに言えば、有明海と不知火海(八代海)を仕切る宇土半島南岸の不知火町にもアコウがありますので、奇妙にも有明海の内側にだけアコウがないことになるのです。
なぜならば、九州西岸で考えれば、それよりも北の長崎県大瀬戸町の松島(松島神社境内)、同じく大島町(大島地区)、前述した佐賀県東松浦郡肥前町(高串地区)、さらに数十キロ北に位置する玄海灘に浮かぶ島、壱岐にもアコウがあるからです。
植物としてのアコウの性質といったことについては全くの門外漢ですので、“有明海の土壌(例えばシルト層)といったものがアコウに適しているのかどうか”などといったことにはほとんど答えることができません。
しかし、このアコウという木の大半が海岸部に分布していることから考えて、“アコウは海と切り離されては生きていくことができない木なのではないか”ということまでは言えるように思います。
ここで考えるのですが、有明海は他の海と比べて堆積(絶えざる陸化のスピード)が異常に大きい海です。現在のように土壌流出が大きくなかった時代、古代とまでは言わないまでも、戦前においてさえも、それなりのピッチで堆積し続けたために、アコウが育つスピードを上回るペースで陸化が進み、結果、海が後退し、アコウは根付かなかったか、大木まで育たなかったように思えるのです。
ここ数百年という単位で考えれば、干拓工事の資材として(実際には加工しにくいので実用にはならないでしょうが、干拓地には一般的に森が形成されないのです)、または、“燃料に乏しい干拓地の宿命として伐採されてしまったのではないか“と思うのです。
いずれにせよ、仮にアコウが根付いていたとしても、有明海で干拓が始まるようになるとアコウは消えていってしまったのだと思うのです。
かつての干拓地というものは、豊かに見えますが、実は非常に資源に乏しく、水、燃料、建築資材(竹、木材、土、その他)の一切が不足していたのです。佐賀平野の半分以上は干拓地ということも可能であり、よく言われる「佐賀んもんが通ったあとには草も生えん」という県民性も、“全てを資源にせざるを得なかった”この干拓地の欠乏性からもたらされたものかもしれません。
つまり、他人の土地に落ちている棒切れさえも持ち帰って燃料にするとか、引抜かれた草さえも持ちかえって堆肥に変えるといった傾向のことです。
こう考えれば、干拓地内の農耕民と言うものは実に貪欲で全てを肥料や燃料にする傾向があり、この結果アコウが根付く間がなかったとも言えるようです。結局、農耕民とアコウとは共存できないのでしょう。
c)有明海を中心に私が見た九州西岸のアコウ分布
九州全体のアコウの分布を全て把握することは、ほとんど不可能ですが、私が確認した範囲(当時)で分布の概略を書いておきます。
【佐賀県】
始めに私が住んでいる佐賀県ですが、東松浦郡肥前町(高串地区)以外には知りません。
【長崎県】
壱岐、五島は魚釣りで過去何度となく訪れたところですが、有川を始めとして多くのアコウが確認されます。その他、車で行ける長崎県内のアコウの生息地としては少数ですが平戸市の獅子地区などを中心に平戸の西海岸などに、大村湾の小串地区や日泊郷などに、長崎市西岸の小江の柿泊から大瀬戸にかけても、島原半島の旧口之津町の早崎魚港の巨大群生地を中心に、旧加津佐町、旧南串山町、南有馬町の海岸部に無数のアコウがあります。
【熊本県】
北から、宇土半島の北岸には住吉神社があります(ここも干拓の陸続きになりましたが、百年前には堂々たる有明海に浮かぶかなり大きな島だったのです)。その沖の小島(『枕草子』に登場する「たはれ島」ですが、「島はたはれ島…」)には五年前までアコウの木が生えていました。その後台風で倒れますが、鳥のおかげでそのうち復活することでしょう。
このような小規模なものは別にしても、天草島原の乱で著名な談合島=湯島の小学校にはかなり大きな群生地があります。私は未確認ですので機会があれば見に行きたいと思っています。
宇土半島南岸には不知火海の再生のために環境保護団体によって多くのアコウが人為的に植えられましたが、海岸保全事業の邪魔になるため熊本県は「生態系にそぐわない別種の植物を持ち込むのは環境に良くない」として排除に動いています。多くの外来の新品種、国外産品を農水省に言われるまま無批判に推奨していることは棚上げにしてですが。ただ、結果としてかなりのアコウが増殖しています。
植林とは無関係ですが、八代市の大鼠蔵島に巨大なアコウが数本、それ以外にも干拓地を中心に市街地にも鳥によってかなりのアコウが増殖しています。さらに南に下ると、葦北郡の田浦町、芦北町、津奈木町の海岸部に無数の小木がいたるところに認められます。
かつては多くの大木があったはずですが、現在それが認められるのは田浦町の隠れ里波多島地区に限られています。
天草にも大木のアコウがあります。一番大きいのは天草上島旧姫戸町の永目のアコウです。これは全国で二番、三番と言われるものですが、私の見たものとしては、これ以上のものが口之津の早崎漁港や鹿児島県の阿久根市の脇本浜や旧串木野市の海岸部にもあるように思うのですが、無論、計測した判断ではありません。その外にも、旧竜ヶ岳周辺、旧松島町、旧大矢野町周辺にも散見されます。上島では旧有明町の無人島黒島に巨木があるとの噂を聞いていますが未だ確認の機会を得ません。下島も旧牛深市の魚貫湾の北岸池田などに相当数認められます。
【鹿児島県】
長島、黒ノ瀬戸あたりからアコウが姿を表し始めます。瀬戸に面した漁港の片隅などにアコウの小木を見つけることができますが、さらに南に向かうと脇本浜にアコウの大木が群れをなしています。現在こそ道路工事や護岸工事で破壊されていますが、ここにはびっくりするようなアコウの巨木があったのです。それを示すかのように多くの切り株が今も残っています。ここから折口浜、阿久根の市街地にも散見されますが、次の群生地は串木野の海士泊周辺になるでしょう。ここにも崖一つを覆い尽くすようなアコウがあります。桜島から垂水にかけても多くのアコウがありますが、象徴的なのは百本のアコウの街路樹です。大隅半島にもまだまだ多くのアコウがありますがこれくらいにしておきましょう。
このように多くのアコウがありますが、これも車で確認できる範囲の話です。船でしか行けないような島や岬にも多くのアコウがあることに疑う余地はありません。
![]()
お断りしておきますが、分布はこの程度のもではなく、人知れない岬や島影に多くのアコウが根付いています。
d)“阿漕”について作業ノートから
“阿漕”という言葉(地名)には、古歌、能(謡曲)の「阿漕」、古浄瑠璃の「あこぎの平冶」、人形浄瑠璃の「勢洲阿漕浦」、御伽草子「阿漕の草子」、西行などの和歌、さらに加えれば、それらを題材にした落語の「西行」といったものまで実に多くの話や伝承そして逸話が残っています。
また、「伊勢の海の阿漕か浦に引網の度かさならはあらはれにけり」といった古歌も残っています。このため、室町以降成立してくる能や浄瑠璃に先行して、「伊勢の阿漕浦」にちなんだ和歌が他にもあったようです。この歌から思うことですが、ここには、漁業権もしくは入浜権を巡る争いが背後にあったと思うのですがいかがでしょうか。
それはともかくとして、和歌で有名な西行ですが(「新古今集」には最多の九四首を残しています)、元は佐藤兵衛尉憲清という名で、禁裏警護役の北面の武士とされていますが、平安末期から鎌倉期の人であり、出家への動機については諸説とりざたされています。
前夜、同族で年嵩の佐藤佐衛門尉憲康と和歌の会から伴に帰り、翌日迎えに行くと急死していたことから出家への道を求めたというのが有力とされているようです。
もう一つは、恋していた絶世の美女堀川の局に「またの逢瀬は」と問うたところ、「阿漕であろう」と言われ「あこぎよ」の意味が分からずに恥じて出家したといった話です。
さて、ここから先は落語の「西行」に出てくる「阿漕」の話です。「……憲清、阿漕という言葉の意味がどうしても分からない。歌道をもって少しは人に知られた自分が、歌の言葉が分からないとは残念至極と、一念発起して武門を捨て歌の修行に出ようとその場で髪を下ろして西行と改名。諸国修行の道すがら、伊勢の国で木陰に腰を下ろしていると、向こうから来た馬子が『ハイハイドーッ。散々前宿で食らいやアがって。本当にワレがような阿漕な奴はねいぞ』。これを聞いた西行、はっと思って馬子にその意味を尋ねると『ナニ、この馬でがす。前の宿場で豆を食らっておきながら、まだニ宿も行かねいのにまた食いたがるだ』『あ、二度目の時が阿漕かしらん』……『伊勢の海あこぎが浦にひく網も度重なれば人もこそ知れ』から、秘事も度重なればバレるという意味。西行はこれを知らなかったから、あらぬ勘違いをした訳である。オチは『豆』が女性自身の隠語なので馬方の言葉から、二度目はしつこいわ、と言われたと解釈した。『阿漕』には後に、馬方が言う意味つまり『欲深』『しつこい』という意味がついた。……」(「千字寄席」噺がわかる落語笑事典 立川志の輔【監】古木優・高田裕史【編】)一応、落語の話はここまでです。
古歌として、「伊勢の海の阿漕か浦に引網の度かさならはあらはれにけり」「伊勢の海阿漕が浦に曳く網もたび重なればあらはれにけり」といったものも残っています。このため、室町以降成立する能や浄瑠璃に先行して、「伊勢の阿漕浦」にちなんだ和歌が他にもあったようです。
謡(うたい)の阿漕(十八ノ四)は、病気の母親に食べさせようとした息子が禁を犯して阿漕ヶ浦(三重県津市の伊勢神宮神饌の漁場)から魚を捕っていたことが発覚し簀巻きにされて海に沈められるという話がベースになっています。
三重県津市阿漕ケ浜から伊勢神宮への御贄(オニエ)を奉納したとされているのですが、漁と奉納とはそれなりの緊張関係があったと思われ、実際に処分された漁師がいたことは事実のようです。こういう背景があって室町期に謡曲の「阿漕」(当然ながら謡曲は古いため、ここでは殺生を業とせざるを得ない漁師の話であって平治の名はなく孝子伝説とは無関係です)が成立し、江戸期になって古浄瑠璃の「あこぎの平冶」が、浄瑠璃 義太夫(**)人形浄瑠璃、の「勢州阿漕浦」が成立し、芝居にまでなります。
このため、江戸の中期から明治にかけて浄瑠璃が大流行し全国に流布されるようになると、単に「アコギ」と呼ばれていた地名が、「阿漕」という表記になっていったのではないかとも思われるのです。
![]()
謡曲 阿漕の教本
多少脱線しますが、釣師の私としてはフィクションとしても密漁したとされた魚が何であったのかが気になります。芝居の中などで平冶が密漁したとされている魚は、くちばしが長く本体も細長い“ヤガラ”とされていますが、日本近海の“ヤガラ”の仲間には“アカヤガラ”、“アオヤガラ”外2種があります。私は阿漕が浦が砂地であることから考えて、“アオヤガラ”ではなかったかと考えています。その外にも多くの興味深い話がありますが、この程度にしておきましょう。
結局、転じてこのような酷い仕打ち(簀巻きにして海に沈める)のことを“阿漕なこと”とまで言うようになったと言われているのですが、では、なぜ、この海は“阿漕が浦”と呼ばれるようになったのかがわからないのです。
e)“阿漕”という地名と“アコウ”
ここで、“アコギ”とも呼ばれる亜熱帯系の常緑高木“アコウ”(赤秀)の存在が気になってくるのです。まず、三重県津市の阿漕を考えてみましょう。
もちろん、現在、ここにアコウの木があるわけではありません。というよりもアコウの生育限界であり北限とされている佐賀県の肥前町高串にはアコウがありますが、その高串から岬ひとつ隔てた“阿漕”地区ではなく、高串港の一隅にある増田神社の付近なのです。
従って、アコウという木と“阿漕”類似地名とを直接結び付るものはありません。
というよりも“阿漕”という地名が残る佐賀県の高串港にアコウが生えていたということが唯一の関連性を示すものかもしれません。しかし、アコウという樹木の分布傾向と“阿漕”関連地名の分布傾向にそれなりの関連性があることからして、アコウと“阿漕”との関係はかなりの可能性があるように思います。
三重県津市の阿漕の話に戻しますが、一般的なアコウの分布から考えて、黒潮の枝流が流れ込む伊勢の海の海岸はこの木の生育領域(であった?)とも十分考えられそうです。
近いところでは、隣県の和歌山県日高郡美浜町三尾にアコウの大木があるようです(龍王神社)。また、三重県内の地名としては、津市の“阿漕”以外にも飯南郡飯高町赤桶(アコウ)、桑名市赤尾(アコオ)、があります。
今日まで、アコウの木と“阿漕”関連地名とを関係づけて論じたものを私は知りません。また、アコウの木の分布領域の中心とされる沖縄や奄美大島に九州などに比較して“阿漕”関連地名が異常に多いということもないようです。もちろん、これはアコウが多いため地名形成の動機としては弱かったとも考えられます。
とりあえず、ここではアコウが松、栂(ツガ、トガ)、榎(エノキ)、栃(トチ)などと同様に、それらが特徴的に見える地域において、松崎、栂尾、榎津、栃川といった地名と同様に、自らの存在を地名として留めている可能性があるのではないかというところまでは言えるようです。
ただし、この木の分布が日本列島の辺境に限定されていたために、“阿漕”という奇妙な表記の地名とアコウの木との関連性が忘れ去られているのではないかと思われるのです。
![]()
天草上島、旧姫戸町永目のアコウ
一般的に漁撈集団は、文字で記録を残さないと言われています。
極めて逆説的ですが、それこそが、アコウや“阿漕”が南方系の漁撈集団がもたらした“樹名”であり“地名”である証拠とも言えるような気がします。
その後も、アコウについて調べていたところ、北限とかいったものを超えて、山口県(いずれも瀬戸内海ですが、柳井市の掛津島、周防大島の東和町水無瀬島)や愛知県にもアコウがあることを知りました。
しかし、愛知県のアコウは“鹿児島から苗を取り寄せて移植した”ようです。
なにやら、民俗学者柳田国男の“ツバキ”の話を思い出しますが、こういったことがあるために、そもそも自然な生育限界とかいったものはなかなか判らないものなのです。
![]()
天草上島、旧龍ケ岳町池ノ浦のアコウ 天草維和島蔵々のアコウ
〇 「アコウ」 クワ科の亜熱帯高木で暖かい海の海浜に生育します。愛媛県西宇和郡三崎町三崎と佐賀県の東松浦半島に位置する東松浦郡肥前町高串の“阿漕”地区が北限とされています。それほど多くはないのですが、九州の南半分の島嶼部を中心にかなりの数のアコウが海岸部に自生しています。
〇〇「義太夫」 室町後期に発生した古浄瑠璃に三味線が加わり江戸期に発展した浄瑠璃には江戸、上方あわせて数十の流派が形成されますが、元禄期の竹本義太夫と近松門左衛門らによって大流行した人形浄瑠璃の義太夫節を特に「義太夫」と呼ぶようになり、さらに関西の浄瑠璃を特に義太夫と呼ぶようになったようです。常磐津、清元、新内節もそうですが、私は義太夫と言えば、上方落語の「どうらん幸助」の影響からか、最近、特に好んで聴くようになりました。「柳の馬場押小路、虎石町の西側に主は帯屋長……(長衛門)」(「特選 米朝落語全集大二十二集」の台詞で有名な浄瑠璃の「お半 長衛門」(オハンチョウ)を思い出してしまいます。 いずれも古川による注釈
さらなる展開
多少ともアコウと阿漕地名との間の関係について理解して頂けたかと思います。
しかし、話はここから新たな展開を見せるのです。古田史学の会代表である水野孝夫氏は、この小論から「阿漕的仮説」(会報69号)という驚くべき仮説を引き出されたのです。詳しくは同会の会報か私が主催するホーム・ページ「アンビエンテ」のリポート106.107号外を読まれるとして(こちらは写真、地図、図表も見ることができます)、『万葉集』に登場する淡海は琵琶湖ではないという議論は、古田武彦氏をはじめとして、万葉集の研究者の間でもかなりの広がりを見せていました。
この議論の中で、古田史学の会の“神様の神様”と言われる西村秀巳氏は『倭姫命世紀』という鎌倉期の文書から“淡海=球磨川河口説”を提案されたのです。そして、ここに注目した水野氏が、伊勢神宮もこの球磨川河口域から移されたのではないかとされたのです。
一方、『古事記』の探求を進められた九州古代史の会の庄司圭次氏は、『「倭国」とは何か』所収の“「淡海」は「古遠賀湖」か”で“淡海=古遠賀湖説”を展開されており、会としても同地が淡海であると考えられているようです。さらに、これがいわゆる新北津論争にも多少の影響を与えているのかも知れません。
ともあれ、まずは、水野代表による「阿漕的仮説」とその解題とも言うべき拙稿「姫戸」を読んで頂きたいと思います。